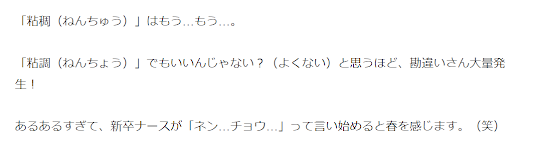IgG4関連疾患という病態がある。診断は集学的に行う。血液データだけを見てぱっとわかるとか、病理組織像だけ見てバチンと診断できるという病気ではない。「合せ技一本」みたいなイメージで。小外刈りで有効、小内刈りで効果、内股で技あり、一本背負いで技あり、合わせてようやく一本! みたいな診断の仕方をする。
ここで我らが病理診断は、決定的な答えを提供してくれるツールにはならない。しかし、昔も今も、有効であることは間違いがない。うまく決まると技ありくらいは取れる。
ただし昨今のIgG4関連疾患における病理診断はどんどん難しくなっている。
柔道のたとえをそのまま続けると、昔はその名の通りIgG4(免疫グロブリンG4分画)というのが診断のカギであり、「一本」に限りなく近い結果をもたらした。免疫組織化学という手法で、病変と目されている部に対して、「IgG4タンパクがあればそこだけ色がつく」という特殊な化学処理を行う。IgG4を持つ形質細胞が、顕微鏡で倍率400倍にした視野の中に10個とか20個とか存在すれば、それだけで「ああ、IgG4関連疾患ですねー」という具合で、診断に大きく近づくことができた。開始40秒、大外刈りで一本である。
でも今はそうはいかない。こんなにシンプルだと精度が保てないことがわかってしまった。
説明が前後するけれど、IgG4というのは、「免疫戦隊グロブリンG」の4番目のメンバーである。G1, G2, G3, G4といて、それぞれ微妙に異なる役割がある。IgG4関連疾患というのは、IgG4がたくさんいればそれで成り立つというものではなく、IgGの4つのサブタイプのうちなぜかG4分画だけが割合多く増えるというのが大事らしい。
つまり「免疫戦隊グロブリンG」すなわちIgG全体を分母とし、IgG4がそのうち何%くらいあるかを検索するのである。ヒーロー大集合モノでピンクの戦士だけが妙に多ければ「なにかがおかしい」と感じるだろう、そういう感じだ。IgG4の総量だけではなく、IgG4/IgGの比を見る。
となれば、自然と、染色1種類だけで検査を終えることはできなくなる。IgG4だけではなく、「IgGすべてに反応する抗体」を用いて、分母の計測をする必要がある。
ただこのIgG染色が激烈に難しい。まさかのトラップである。IgG4はむしろ簡単に染めることができるのだが、IgGを正確に・きれいに染めようと思うとコツが必要になる。この段階でいくつかの検査室では、「病理組織中のG4分画の割合? なんか……よーわからん」となってしまう。一本どころではないのだ。
それだけではない。別の問題もある。というか、次に語る内容こそが、「病理診断だけで技あり以上をとるのが難しくなってきた理由」であると考えている。
IgG4関連疾患に類似した病像を示す、ほかの疾患がある。たとえば「特発性形質細胞型リンパ節症 idiopathic plasmacytic lymphadenopathy (IPL)の病型をとる特発性他中心性キャッスルマン病 idiopathic multicentric Castleman disease (iMCD)」、すなわちiMCD-IPLという病気だ。うんざりしただろう。大丈夫、私もこの話をするときはいつもうんざりしている。
IPLとかiMCDだけではだめなのか? と聞かれることもあるが、歴史を知っていると、ごめん、だめなのだ、とお答えせざるを得ない。一時的に曹操の下にいたときの関羽が顔良と文醜を斬ったがこのとき劉備は袁紹の下にいたので、関羽は劉備の仲間を斬ったことになる、けれども関羽からしてみれば「あくまで一時的に曹操の客将であったに過ぎず心は劉備の下にあった」と言いたくなることだろう。そこを省略して「関羽は劉備の同僚を斬った」とは言わないのと一緒だ(?)。「曹操配下時代の関羽」と限定する感じで「iMCD-IPL」と言ってはじめて伝わる義兄弟の情みたいなものがある(???)。
さてiMCD(-IPL)はIgG4関連疾患とは治療法が異なる。IL-6受容体拮抗薬であるトシリズマブなどを使うことがある(と聞いている)。したがって、きちんとIgG4関連疾患とは区別しなければいけないのだが――
/) /)
( 'ㅅ')
どうせ誰も読まなくなったタイミングで
登場する突然の無意味なうさぎ
じつはいやらしいことに、先に述べたIgG4免疫組織化学やIgG4/IgG比などは、iMCDでも異常となりうる。これまで大半の病理医は、「IgG4を染めて、IgGと比べてくれればいいですよ」などと言われてその通りやっていたのだが、この検査結果が陽性だったからといって、IgG4関連疾患と決めつけることはできなくなった。一番見分けたい別の病気を見分けることができないからだ。したがって病理医は、機械的にIgG4の免疫組織化学をして検討するだけではなく、もっと虚心坦懐に、細胞のおりなす配列やら高次構造やら、全体のテクスチャやらアーキテクチャやらをたくさん見て考えなければいけない。
しかしいまさらIgG4関連疾患とiMCDの細かい差を見分けてくれと言われても、これまでぬるく診断していた病理医のスキルはそこまで育っていない。
これらを見分けようという試みはこの10年ちょっと、一部の重箱の隅でコマゴマチクチクとやられてきたのだけれど、その試みをすべての病理医が追いかけていくというのはどだい無理な話だ。専門性が高すぎる。
しかし、それでもやる。なぜなら、主治医が、「なんとか見分けられないか」と言うからだ。超・専門家ではなく、われわれ、市中の病理医に対して願うからだ。
しょっちゅうあることではない。しかし、たまにある。数年に一度くらい。
「IgG4だと思うんですけど鑑別はiMCDです、病理組織学的に特異的所見ありますか?」のような依頼書が舞い込む。出、出~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~何意味不明特異的所見探訪所望奴~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~と思うがむりもない。臨床医を責めてもしょうがない。
とにかくこの病気の診断は「合せ技」だ。ただし診断においては、主治医がひとりですべての「技」をかけることができるわけではないということなのだ。小内刈りで重心を反対側の足に寄せておいたところに内股をしかけてふんばるところを一本背負いするから一本が取れる。できれば小内刈で効果を、内股で有効をとっておけば、相手はゆさぶりから必死で逃れようとするから、最後の一本背負いで技あり以上がとりやすくなる。このような「順を追って退路を断っていく」ような診断をするにあたって、小内刈りと内股までは主治医ができるが、一本背負いだけは病理診断が担当しなければいけない、というイメージだ。おわかりだろうか? 診断は柔道とは違うが、たとえをこのまま続けると、「襟から手を離して袖を引っ張り込めるのは病理医だけ」みたいなことがたまに起こる。花筵状の線維化や閉塞性静脈炎を見つけつつ、好中球や壊死などの陰性所見がないことを念頭に、IgG4陽性細胞の比率や分布をちまちまカウントしていくという技術は、言ってみれば「最後に一本背負いが来るとわかっている相手をそれでもぶん投げるためのキワキワの一本背負い技術」だと言える。主治医は一本背負いに関しては病理医に「外注」し、あるいは自らは巴投げや横四方固め、奥襟じめなど別のやりかたで一本を取れないかと、私たちに外注して少し楽になった分で、虎視眈々と違う技のかけかたを考えている。そういう難しい状況で、「一本背負い行けそうならぜひ行っちゃってください!」と「外注」されているのが私たち病理医なのだ。私たちはそれを意気に感じる必要があるし、時代の要請に応えてその時点での最高のスキルで技をかけていく必要がある。まあ診断は柔道とは違うんだけど、だいたいそういうイメージで――
――あっ剣道に例えることもできるな、北辰一刀流の「セキレイの尾」を現代風にアレンジして、表の面に視線をあわせたあと裏の小手に行くと見せかけて裏からの面に飛ぶときの「小手をちらちら意識させる」部分が病理医である、みたいなたとえも、あっいや逆胴のほうが伝わるだろうか――