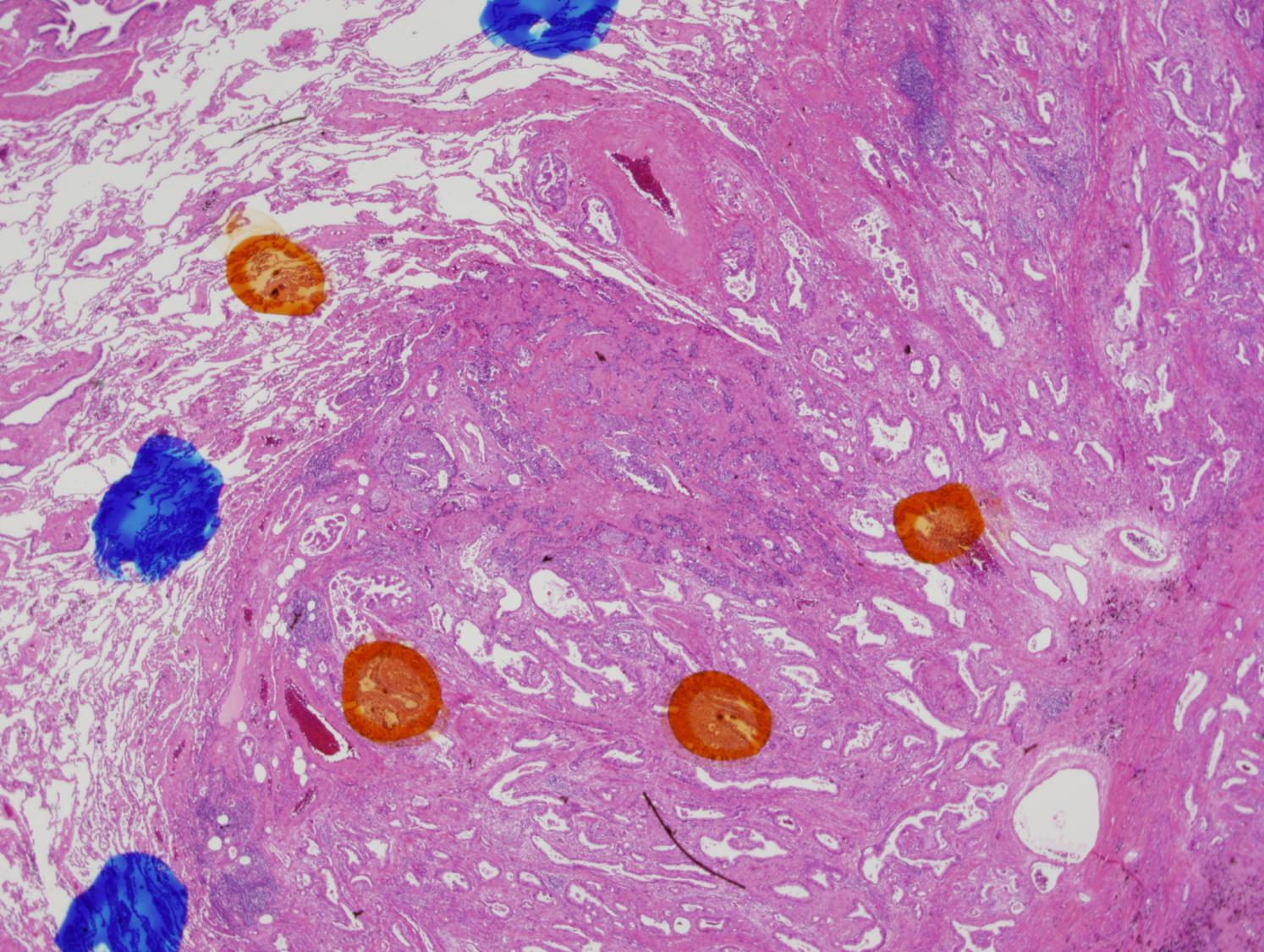ワンピースの108巻がコンビニに並んでいる。けっこう前に発売されたはずだ。ググると3月の上旬が発売日であった。いまだにあれだけ並べても売れる可能性があるということだろう。ちなみにぶっちゃけ買い忘れていた。毎週ジャンプで読んでいるのでコミックスの先をすごく楽しみに待っているというわけではないが、やはりコミックスで通して読んだほうが情報がまとめてドカンとやってきておもしろいタイプのマンガだ。ほくほく買う。飽きずに並べておいてくれたおかげでこうして助かる人間がいる。
コンビニの本棚のスペースは限られている。ワンピースのほかには呪術の新刊とコナンのムック(映画が出ているからだろう)が目に付くくらいだ。種類を増やそうと思えば増やせるのだろうが、とにかくワンピや呪術やコナンの新刊を複数ずつドカンドカンと並べて陳列効果を増している。コンビニなんだからこれでいいという徹底した戦略だ。ワンピならコンビニで買えると思わせたのはうまいとも思う。
かつてはゴルゴとか山口六平太とかがよく置いてあった。山口六平太! これふつうに予測変換で出るんだな! あとはBARレモン・ハートとか、日本酒をだらだら飲むやつ(名前忘れた)とか。それがいつしかワンピのコーナーになっていた。コンビニを訪れる客層も変わっているということか。むしろワンピの読者は往年のゴルゴの読者っぽいのだろうか。
昔、釧路駅の中に古本屋があった。地方の主要駅の構内に古本屋があるというのはかなり思い切った構成だなと思うが、札幌までの特急スーパーおおぞら4時間10分を車内販売のお茶だけで過ごすのはしんどく、カストリ雑誌や古本をそこにねじこんでいったらどうかという提案には納得感があり、私は毎月特急に乗る前にその古本屋で2冊くらい本を買ったし、店内は似たような客でそこそこ賑わっていた。
1冊はゴルゴ。
定価300円くらいの、表紙の紙が薄くてカバーのかかっていない、いわゆるペーパーバック形式のもの。MY FIRST BIGとゴシック体で印刷されているやつ。古書だとだいたい150円弱で買える。状態が悪いと100円。その程度の割引率というのがいかにも駅の古本屋だなあという感じ。毎月のように購入して数年、ほとんど直感的に選んで買うのに、なぜか1回もゴルゴの「ダブり」を経験したことがない。
思い返すと不思議だ。
もしかすると、もしかしなくてもだけれど、あの古本屋にゴルゴを売っていた人はたった1人だったのではないか。札幌から釧路に向かって出張する人が半分定期的にゴルゴのペーパーバックを持って乗車し、到着地である釧路駅で売るのを、私が毎月買い続けていたというパターンがありうる。そうでもなければあの見た目に区別がつきづらい「コンビニゴルゴ」の品かぶりが何年にもわたってゼロだったということに説明がつかない。おそらくだが札幌か釧路に縁のある人の中にひとり、私とまったく同じペースでまったく同じ内容のゴルゴを読み続けてきた人がいる。
そしてもう1冊は小説。
まあ何度か自己啓発本みたいなものも試してみたのだけれど、やはりあまり肌に合わず、小説に落ち着いた。
そもそも古本屋にある自己啓発本というのは、発売直後にドンと売れて話題になり、テレビやラジオなどでさんざんっぱら内容をこすり倒され、すっかり旬を過ぎてから店に並んでいるもので、時代の選択圧に耐えられるだけの腰の強さがないとすぐに感じた。だから自然と小説となった。
小説。『ハイペリオン』や『月は無慈悲な夜の女王』などの早川の水色、あるいは京極夏彦の判型でおなじみ講談社ノベルスなどをよく購入した記憶がある。乗車時間が長いから多少分厚い本でも読める。ただし出張帰りにあまり荷物を増やしたくないので単行本には手を出さない。山田風太郎をいつ読もうかなと毎月悩んでいた(結局読まなかった)。椎名誠の新宿赤マントシリーズがいつも同じ場所に並んでいた(私は持っていたので買わなかった)。
釧路を出て、白糠、池田あたりでゴルゴは読み終わってしまう。そこでいったん寝落ちして、帯広駅でばたばたと人が降りたり乗ったりする音でまんじりと目が覚めてまた寝直す。新得、トマムのどちらかでまた目が覚めてそこから小説を読むとなると残りは1時間半といったところだ。そこから小説を読む。だからいつも中途半端なところで札幌にたどり着く。へたをするとそこから1か月、次の出張まで続きを読むのがおあずけになったりもしたはずだ。『ハイペリオン』はそういう読み方をした。あまりいい読み方ではなかったと思う。
釧路から帰ってくるときはどうしても疲れているからそういう断片的な読書になる。ゴルゴがちょうどいいのだ。行きはまだ元気なので札幌で乗車してからじっくりと本を読み続けることができた。そうやって読んだあの本、名前はなんといったかな、ハヤカワのSFということ以外まるで思い出せないのだが、がんばって検索を繰り返す。ハヤカワ SF 異種姦……鳥のイメージ……街……。どうやっても名前が出てこない。まいったなあと思ってふと、前にやっていたブログの内部検索をかけたら出るのではないかということに気づき、ブログ内検索に「SF」と入れてみたらすぐに出てきた。ペルディード・ストリート・ステーション。
https://dryandel.blogspot.com/2020/12/blog-post_15.html
やっぱり釧路の話をしている。
読書の印象として後々まで残っていくのが、本の中身より「その本をどこで読んでいたか」という環境のほうだったりするのは、思えばちょっと悔しい。真の読書家というのはきっとそうではないのだろう。でもしょうがない。あのころも今も、私の脳は思索よりも旅をしていた。